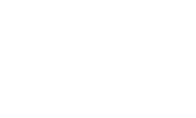能楽の未来を担う若手能楽師が流儀の垣根を越えて集まり、現代と伝統の世界とを結ぶ注目のプロジェクトBunkamura30周年記念「渋谷能」。第四夜の公演レポートをお届けします。

2019年7月16日(火)|事前講座
第四夜を数える「渋谷能」の事前講座は、「不条理」をテーマにお話と実演がたっぷりの催しとなりました。まずは、本公演で地頭(じがしら)を勤める和久荘太郎師がひとりでお出まし。シテの髙橋憲正師とは2歳違いで、ずっと一緒に修行を続けてきた仲間だそうです。
宝生流にとって『藤戸』という曲は、若手から中堅にかけての能楽師が気軽にできる曲ではなく、今回は「渋谷能」という特別な公演だから、という理由でお家元からお許しが出たそう。また、ご自身が勤める地頭も非常に重要な役とのことで、「自分でハードルを上げてしまったかも」と仰いつつも、能楽という到達点のない世界で未熟と思われるのを覚悟の上でぶつけてやろう、という思いを語ってくださいました。
『藤戸』は『平家物語』から材を採った曲。その“前段”にあたるストーリーの説明がありました。源平合戦も終わりに近づいた頃、備前国(今の岡山県東部)の藤戸という場所が舞台。源氏の武将・佐々木盛綱は、自分の手柄のための口封じとして、馬で渡れる浅瀬を教えてくれた漁師を刺し殺すのです。能『藤戸』ではその後、手柄の恩賞として得た藤戸の地に赴任した盛綱(ワキ)の元に、殺された漁師の年老いた母(前シテ)が訴え出るところから始まります。悲嘆にくれた老母の姿に後悔の念にかられた盛綱は、男を殺したのは自分であると告白し、管弦講を催して弔うことにしました。物語の後半では、殺された漁師の霊(後シテ)が杖をついて現れ、自分が盛綱に殺される場面を「仕方話」という一人芝居の形で再現していくのがポイントのひとつ。やがて、漁師の霊は盛綱の弔いに触れ成仏に至るのですが、『平家物語』ではただ「殺された」としか書いていないこの男を、作者の世阿弥は老母を出して話を展開させていることから、『藤戸』は鎮魂の要素が大きいといいます。現代的にいえば反戦的なお能かもしれないという見解もお話しされました。
続いて謡の体験です。まず和久師のお手本を聞いてから一緒に声を出していき、盛綱、老母、漁師の霊それぞれの登場シーンに挑戦しました。声の出し方や抑揚など、プロの能楽師のように謡うのはかなり難しいですが、二回三回と繰り返すうち、少しは謡えるようになった気がしました。
講座も後半に差し掛かったところで、シテを演じる髙橋師が登場。後シテが使うという杖を持ち、実演を交えて後シテの動きを “解剖”していく試みです。竹で作られた杖は、漁師の霊が地獄からやってくるための“寄る辺の杖”。地謡に合わせて杖をつく、向きを変える、両手で杖を持つ、遠方を見るなどの動きを披露します。後シテが演じるのは、理不尽な最期を迎える自分とかつての盛綱の一人二役。盛綱が男を刺す場面では、杖を刀に見立て、両腕で自分を抱え込むようにゆっくりと動きます。まるでスローモーションのようなこのシーンは、残像現象を意識して演出されているのではないか、とのこと。その他、男が海に浮き沈みする様、彼岸への旅立ちなど、解釈が難しそうな場面を中心にお話がありました。

▲後シテの動きを“解剖”する和久師(右)とシテ・髙橋師
最後は、シテと地頭をそれぞれに勤めるお二人が意気込みを語ってくれました。
「『藤戸』は非常に悲しい物語。シテを通して、皆さんの経験や想いを重ね合わせて観ていただきたいです。和久先生にはどう謡っていただけるのか、僕はどう応えるのか。『俺はできるんだぞ!』という戦いではなくて、僕たちがそれぞれにこう思っているということを皆さんにどう伝わるか、という戦いはしていきたいですね。」(髙橋師)
「『藤戸』は季節が春、そして夜。夜である、春であるということを謡の力、要素として出してこなきゃいけない。謡が荒くなりがちな曲ですが、しみじみと染み渡るようなものができたらと思っています。またこれでハードルを上げていますね(笑)。」(和久師)
*講師:和久荘太郎(シテ方宝生流)、髙橋憲正(シテ方宝生流)
*会場:セルリアンタワー能楽堂
2019年7月26日(金)|第四夜 宝生流『藤戸』
静かになった空間にお調べが流れ、舞台が始まります。
囃子方、地謡の着座の後、佐々木盛綱(ワキ)が家臣(ワキツレ)とともに登場。名乗りの間にも、勝ち組である源氏側の盛綱には、晴れやかな雰囲気が漂います。新しい領主として民の訴訟があれば聞いてやろうという寛大な態度を示しながら、ワキ座の床几(しょうぎ)に落ち着きました。
再びお囃子が響き、場の空気が変わりつつある中、前シテである年老いた女が現れました。かつて盛綱がこの藤戸で平家と戦った際、手柄を立てるために漁師の男から情報を得ながらも、男に褒美を与えるどころか殺めてしまった―その男の老母です。哀れなほどにやつれた姿で、しかし意を決したような着実な歩みで近づいてくる老母。やがて盛綱の前で我が子が海に沈められたことを訴えます。実は心当たりのある盛綱は、さらに老母に詰められると明らかに狼狽します。老母のやりきれない気持ちを語るような地謡が始まり、とうとう観念した盛綱は、一句一句を絞り出すように過去を語ります。
この生々しい独白シーンは、ワキにとって見せどころでもあります。手柄に繋がるよう、馬で渡れるような浅瀬の場所を漁師の男から聞き出したものの、素性のよからぬ者なら他の誰かにも話すかもしれない。気の毒ではあるが……と思いながらも、自分の手柄を優先させ、男を殺めた盛綱は、とうとう老母に男を二刀で刺して海に沈めたことを告白します。息子の死の噂は本当だったのか。老いた身に辛い現実を突きつけられた老母の心情を、再び地謡が穏やかながらも切々と謡っていきます。老母は、この世は辛いと悲嘆にくれる様を見せますが、同時に理不尽な仕打ちに対して抑えていた感情が高ぶり、同調した地謡のテンポが段々と早まります。ついに老母は我が子を返してほしいと盛綱に掴み掛かろうとして、狂わんばかりの嘆きをぶつけるのです。
取り縋る老母を撥ねつけた盛綱でしたが、絶望の淵に追いやった相手を見捨てるわけではありません。漁師の男を弔うからと自らの下人(アイ)に家まで送らせます。老母が去った後、盛綱は武門のならいとして浦の男を殺してしまったが、あまりにも不憫であると漏らします。そこで管弦講を行うこと、7日間は浦々の網をあげさせて殺生禁断と定め、弔いの準備を始めます。手柄のためとはいえ、戦の敵ではない一漁師を手にかけてしまったことへの盛綱の改悛の情が見える場面でした。
お囃子の音が後場の始まりを告げ、盛綱とその家臣が管弦講を催している場面になります。管弦講の音楽に惹かれるように、漁師の霊(後シテ)が静かに現れました。やせ細り荒みきった姿で、力を振り絞って歩いてきます。身勝手な理由で殺された怒りや恨みを押し殺したかのように、寄る辺である杖に頼って橋掛かりをゆっくりと進んできます。コツ……コツ……と近づいてくる杖の音は重苦しく、歓迎すべき客の足音ではありません。おもむろに自分の理不尽な最期を思い出すまいと思う心が物憂いのだと話し始めました。
注目したいのはシテの演じ分けです。それまで年老いた女性だったシテは、ここからは幽霊とはいえ若い男性に。演技者は同じなのに、前半と後半では声色も歩き方も全く違う人物に見えてきます。
盛綱たちの前に現れた男の幽霊は、弔いについて感謝はするがどうしても恨みを消せず、妄執となって迷い出てきたのだと言います。盛綱の今があるのは自分のお陰ではないか、何も悪いことをしていないのに、海を渡る浅瀬を教えたことで自分が三途へ渡る羽目になったと理不尽さを深く、静かに訴えます。

▲能「藤戸」髙橋憲正(撮影:辻井清一郎)
やがて男の幽霊は、盛綱に手を掛けられた様を仕方話で再現します。緊迫した状況を謡う地謡にのせて、シテは向きや杖の持ち方を変えました。盛綱が刺した二刀に見立てて刺し通すさまを二度。陰惨な場面であるはずなのに、シテの鮮烈な動きに引き付けられました。絶命した男は海に沈められ、波が揺れるに任せてその身体が浮き沈みする有様までもありありと見せつけられます。
無念の最期を語り終えると突然、男が盛綱に詰め寄ります。
「恨みをなさんと思ひしに」
これまで抑圧されていた強い恨みが発露した一瞬。しかしそれはもう過去の話。ハッと我に返ったように後ずさり、管弦講という篤い弔いによって救いの時が来たことを知ります。自分を刺した刀に見立てた杖は、今度は彼岸に渡る舟の棹となりました。先ほどまでシテから発していた殺気は消え、舟に乗り込む足取りに重さは感じられません。ようやく重苦しい不条理の念から解放され、苦しみが昇華できたと救いを見た気持ちになったのではないでしょうか。
-
今回も終演後はアフターパーティーが行われました。出演者の挨拶の後、参加者との活発な交流で盛り上がり、次回以降の公演にも期待が寄せられました。