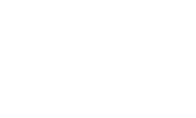能楽の未来を担う若手能楽師が流儀の垣根を越えて集まり、現代と伝統の世界を結ぶ注目のプロジェクト「渋谷能」は今年で3年目を迎えました。喜多流・宝生流・観世流それぞれの公演とシテ方五流儀と和泉流狂言が揃う千秋楽の全四夜を開催します。
公演レポート第一弾は第一夜をお届けします。事前講座の動画も公開しておりますので合わせてお楽しみください。
2021年7月15日(木)|事前講座
第一夜『氷室』公演に先立ち、事前講座が催されました。講師は今公演でシテをつとめる喜多流の佐藤寛泰師。最初に「人前でしゃべることを得意としない」と仰っていましたが、最後まで非常にわかりやすくて興味深い内容で充実した講座でした。
能『氷室』は、演じられることが少ない曲目なのだそうです。氷室とは、冬の間にできた氷が保存される場所で、昔の人々は夏になると氷室から取り出された氷で涼をとったり、甘葛(あまづら。樹木を煮詰めて作る甘味料)をかけてかき氷にしたりしたものでした。現在のように冷凍庫などない時代ですから、夏の氷は非常に貴重なもの。氷室の恩恵を受けられるのは皇族や貴族階級で、口にすることで延命効果や霊験あらたかものといわれていたようです。
続いてストーリー解説。舞台では氷室を模した作り物が置かれていて、亀山院の臣下たち(ワキ・ワキツレ)が丹後の氷室山へ向かうところから始まります。そこで出会った氷室守の老人(前シテ)と若い男(前ツレ)から氷室のいわれを聞き、さらには氷御調(ひのみつき)というお祭りを見るように勧められます。氷室が仁徳天皇の御代のころからあり、神の威徳と帝の恩恵のお陰で夏になっても氷が残って朝廷へ納められることが語りや謡で伝えられます。物語の後半では天女(後ツレ)、続いて氷室明神(後シテ)が現れて臣下たちに氷を帝の元へ運ぶよう促し、天下泰平を寿ぐという展開となります。
講座では面(おもて。能面のこと)の紹介もありました。ここで『氷室』の前ツレでご出演のシテ方・谷友矩師も舞台に登場。まず取り出されたのは「小尉(こじょう)」の面。尉=お爺さんのお顔のなかで最も品位があり神聖なものを舞う際にかけられるそうです。もう一つ見せてくださったのが「三光尉(さんこうじょう)」。こちらもお爺さんのお顔ですが、俗っぽいお役の時に使われるとのこと。並べて見せていただくと、同じ尉面でも雰囲気が全く異なることがわかります。次に紹介されたのは「小面(こおもて)」という若い女性の面。こちらは未婚・十代半ばの女性の顔で、今回は後ツレの天女に用いられます。後シテの氷室明神で使うという「小癋見(こべしみ)」は架空のお役を表すということで、「大癋見(おおべしみ。小癋見より表情が大きい」)や「癋見悪尉(べしみあくじょう)」といった他の癋見面と比べての解説に感心が高まりました。
▲癋見を披露する佐藤師
講座の最後は仕舞『氷室』の実演で締めくくられました。仕舞は能の曲目の見どころを切り取って簡略化されたもので、通常は紋付袴の姿で舞われます。ここでは物語のラストでシテが氷を捧げて献上する場面の舞が披露されました。氷を表しているのでしょうか、銀の扇を持っての舞に荘厳さが感じられました。
▲仕舞を披露する佐藤師と地謡を務める谷師
講座の後は質疑応答のコーナー。参加者からの質問に一つ一つ答え、曲目への思いも語る佐藤師に、公演への熱い意気込みも感じられました。
※講師:佐藤寛泰師(シテ方喜多流)
※会場:セルリアンタワー能楽堂
事前講座の動画はこちら
2021年7月30日(金)|第一夜 喜多流『氷室』
今年度の第一夜は喜多流の『氷室』。能楽評論家の金子直樹先生と女優の石田ひかりさんの解説から始まります。拍手で迎えられて舞台に登場。今年度のテーマは「雪月花」。第一夜の公演は「雪」を表す『氷室』です。また今後の公演予定は、「月」の『山姥』(宝生流)、「花」の『三山』(観世流)と紹介されました。
『氷室』を映像で見たことがあるという石田さんは、「特にドラマチックな展開ではないけれどずっと楽しめる。早変わりなどもあり、とにかく盛りだくさん」という感想をお持ちだそうです。金子先生からは、天然の冷蔵庫で氷を貯蔵する氷室の説明や曲目、舞台に出てくる作り物の解説などがありました。
休憩を挟んで舞台が始まりました。舞台には一畳台と呼ばれる台座が置かれ、その上に黒い布で覆われた山のような作り物が載せられます。これは氷室を表しています。囃子の笛や鼓の音で場の空気が整えられ、能楽堂全体が物語の世界へと引き込まれました。
揚幕から舞台へ現れたのは、亀山院の臣下(ワキ)とその従者たち(ワキツレ)。勢いのある名乗りに帝に使えるものとしての威厳が感じられます。丹後・九世の戸から都へと帰る途中、氷室山に出たようです。そこへ現れたのが若い男(前ツレ)と老人(前シテ)。雪かきをする道具である「朳振/柄振(えぶり)」を持っています。臣下は老人に「毎年氷室から氷が献上されているのは知っているが、実際の氷室を知らない。夏も氷が保てるという氷室のいわれを教えてほしい」と尋ねます。老人は氷室の由来を語りながら、朳振で雪をかき集めては氷室へ運んで氷として保存する様を見せます。また氷室は古代の仁徳天皇の時代からあり、いくつかの地で環境の整った場所に定められている、と。臣下はさらに興味を示すと、老人は氷室があるのは帝の御威光のお陰でもあると続けました。シテの謡は地謡と掛け合いになり、その後地謡が承けていきます。
老人の話に納得した臣下が帰ろうとすると、老人は夜に氷室の氷を供える氷御調(ひのみつき)の祭りがあるから見ていくよう勧めます。気が付くといつの間にか老人は氷室の中へ消えていったようでした<中入>。作り物の後方から中に入ったシテは、ここで後シテの氷室明神の姿になるために面や装束を替えることになります。
この間、雪を凍らせる様を見たいという臣下の要望に、社人(アイ)が登場してお囃子に合わせて謡やコミカルな舞を披露。アイの二人が持つ銀色の扇は、雪や氷をイメージしたものでしょう。雪乞いの甲斐あって降り積もる雪を集める二人。ときどき息で手を暖めながら、丸めた雪を転がして大きな塊を作り氷室へ納めていくのでした。
そして舞台は後半。囃子に太鼓が入り、地謡に合わせ後ツレが天女の姿で本舞台へと現れます。場を浄め、寿ぎ、じっくりと見せてくれるような中之舞です。しばらくすると、作り物の中からシテの謡が聞こえてきました。地謡と交互に謡い繋がれていきます。作り物の布が下げられ、氷室から現れたのは赤頭に小癋見という姿の氷室明神(後シテ)。氷を表す金色の小さな小物を両手に大事そうに持ちつつ、身体を颯爽と翻して舞い始めました。威勢のいい囃子の音とともに舞う舞働(まいばたらき)です。本舞台だけでなく橋掛かりにも移り、所狭しと勇壮に舞います。最後にシテが氷を捧げる際、慎重に手渡す様子も目を引きました。氷が大変貴重な宝であり、またこれを御調として捧げることができる世の太平を、舞台を観ていた皆さんは感じたことでしょう。
▲能「氷室」佐藤寛泰(撮影:辻井清一郎)
能の後は小鼓方幸流・成田達志師と喜多流シテ方・友枝雄人師の進行でのアフタートーク。途中からはシテをつとめたばかりの佐藤寛泰師も加わり、大いに盛り上がりました。
■「渋谷能」で『氷室』を舞うという巡り合わせ
これまでの「渋谷能」で脇能は出ていませんでしたよね。通常の能楽公演は“コア”な、能楽をよく知っているお客さんが多いと思うんです。例会などで脇能があっても、観たことがある、知識があるという方ばかりですが、「渋谷能」では初めて能を観るという方が多くいらっしゃる。だから『氷室』に決まって一瞬「脇能ってどうなのかな?」と考えました(笑)。
僕自身、『氷室』を舞うのは2回目です。1回目は公演ではなく、6年くらい前かな……稽古のなかで装束を付けて舞いました。喜多流でもよく出る曲目ではありません。個人の会でもなかなか選ぶことのないものなので、「渋谷能」で舞う機会がまわってきたのは、自分のような年代の者でもやっていったほうがいいということなのでしょう。巡り合わせなんでしょうね。
■能の原点に帰る「脇能らしさ」
『氷室』という曲目は、おそらく急に作られた脇能の作品っぽいんですよ。時の帝が亀山院。1300年代の方ですが、観阿弥・世阿弥の時代から50年くらい経ってからの人なので、何か必要があって作られたのではないかと。他の『高砂』などは、故事などがもっと盛り込まれていますが、『氷室』は結構あっさりしているというか。
『氷室』の稽古をしていくなかで、脇能らしい謡い方を意識して強く謡うのが脇能だと考えています。「脇能らしさ」とは何かと問われると……一本芯の通った強さ、ハキハキとした謡い方ではないけれども歯切れのよさは必要。表面の強さというよりも内面に保たれている強さとでもいうのかな。例えば座った姿勢から足だけで向きを変える動作でも、ワキに向かって語っている姿、代弁で地(地謡)が謡うわけですけれども、そのときに大きいものが動くような。ただクルリと向くのではなくググッと大きく盛り上がるような感じが必要なのではないかと。
何か細工して見せるものではないと考えています。型もそう多くないし、色を付けるというよりも、能の原点に帰る――立ち方、摺り足、足を摺るというよりもドシッとしたなかにも軽妙さも感じ取れるような。どう表現するべきか難しいけれども、そうできるようにしたいです。
■すべてが揃って初めて見える情景
このようなご時世にもかかわらず「渋谷能」の公演が催されたこと、足を運んで観にきてくださった方々、安全に公演できるようにしてくださった関係者の皆さんへのお礼といいますか、そんな想いを込めて舞いました。また実際に『氷室』を舞ってみて、能の原点や基礎的なものが強い柱となり「自分の考えでこうする・したい」というものは弾き飛ばされるような、入る余地がないと実感しました。
稽古ではお囃子は無く謡手(うたいて)と舞人(まいびと)だけですが、本番ではおワキがいて、お囃子も入る。静かな時には締めていく、掛かっていく時にはお囃子もリズムよく。そこで初めて情景がより色濃く映し出され、場面がクリアになっていくのを強く感じました。これらに助けられてシテは舞っているのだとあらためて思いました。

■入り口はいろんな方向へ開いている
事前講座でも言いましたが、僕は解説するのが好きではないんです(笑)。でも必要にかられてやってはいますよ。調べ物していると、曲目に関するような新しい発見があります。例えば『氷室』関連では、昔は夏に氷で暑気払いなどできなかった庶民が、氷を模した「水無月」というお菓子を食べるようになったとか。毎年何気なく食べていたものなのだけれど、「あぁ、これは氷からきているものだったんだ」と気付かされる。そんな話でも能の見え方、楽しみ方も深まってくるように思います。事前講座や手引きは演者も参加者もお互いに学べるなんてことがあっていいですよね。
お菓子といえば、「渋谷能」では本和菓衆(ほんわかしゅう)さんが『氷室』にちなんだお菓子を考案して、お客さんへのお土産に用意してくれましたよね。そこから能に興味・関心がわいたら面白いです。いまは“入り口”なんていろんなところにあります。そしていろんな方向へ開いています。だから「これを観なければいけない」なんて固くならなくてもいいんです。どこからでも入って、気軽に観ていただければな、なんて思います。